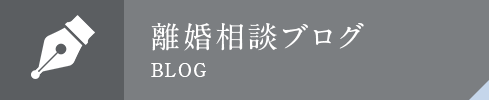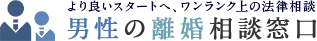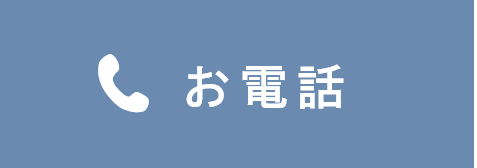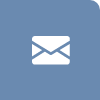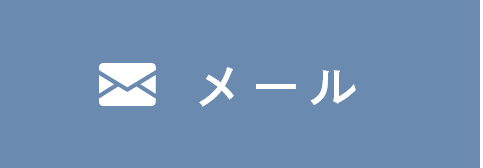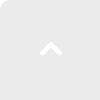「連れ去り」よりも恐れるべきこと
2023.03.18更新
「連れ去り」という言葉があります。
配偶者が突然、子を連れて別居する行為を指します。
別居と同時に代理人から受任通知が届き、配偶者と連絡が取れなくなる。
子の親権を失う前提での離婚協議を余儀なくされる。
そういった一連の流れを含め「連れ去り」という言葉が使われることもあります。
少し前まで、いわゆる「連れ去り」にあった方からの相談は非常に多かったです。
しかし、最近になってやや減っている印象があります。
件数が減っているだけでなく、連れ去りの態様もあまり乱暴ではなくなってきているようにも感じます。
弁護士からの受任通知の文言も、以前よりソフトになってきてもいるようです。
その代わり、最近増えている印象があるのが「追い出し」です。
配偶者から、自宅から出て行くよう求められる件が増えているように感じるのです。
「追い出し」は「連れ去り」よりもさらに深刻です。
家庭を失うだけでなく、自宅まで事実上失うことになりかねないからです。
「追い出し」は、子の意思を盾に行われることもあります。
子もあなたに出て行ってほしいと言っている。
子のためにも、出て行ってくれ。
そう言われると、子を大切に思う人ほど抵抗は難しいでしょう。
場合によっては、子の口から直接「出て行ってほしい」と言わせる人もいます。
子を離婚紛争に巻き込まないためにも、自分が身を引いたほうがいいのではないか。
そう考えるのは、思うツボです。
「追い出し」でさらに深刻なのは、追い出された当人がしばしば「自分の意思で出て行った」と思っていることです。
家を出る経緯をよく聞くと、追い出されたとしか思えない。
相手には、明らかに配偶者を追い出す意図があった。
それでも、最後は自分から家を出た以上、自分は追い出されたのではない。
「追い出された」自覚がないと、対応に後手を踏むことになりかねません。
さらに悪いのが、裁判所含め第三者も、「追い出し」被害者を「自分で家を出た人」と判断するケースが多いことです。
実態をきちんと見極める必要があります。
最も恐れるべきは「連れ去り」よりも「追い出し」です。
家を出てしまう前に、まずご相談いただければと思います。